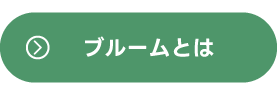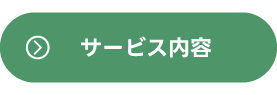発達障害の方の就職 7つの事例で見る職場での働き方
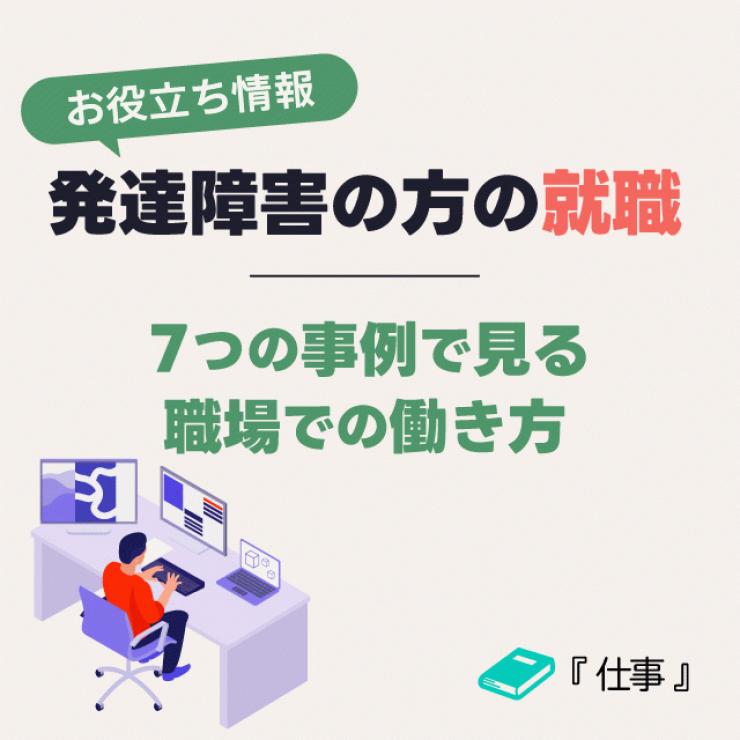
発達障害のある方が就職を考える際、自分の特性を理解し、それを活かせる職場環境や働き方を見つけることが重要です。この記事では具体的な7つの事例を通して発達障害の特性と職場での働き方について詳しく解説します。
発達障害の種類について
発達障害は生まれつきの脳機能の偏りによって起こる障害で、主に以下の3つのタイプに分類されます。
ADHD(注意欠陥多動性障害)
注意力の維持が困難で、多動性や衝動性の特徴があります。集中が続かない、じっとしていられない、思いついたらすぐ行動してしまうなどの傾向があります。一方で、興味のあることには高い集中力を発揮し、創造性や発想力に優れている場合も多くあります。
ASD(自閉スペクトラム症)
ASDは「対人関係の苦手さ」と「こだわりの強さ」が主な特徴で、相手の気持ちを読み取ったりその場の空気に合わせたりすることが苦手な一方、特定の分野に強い興味や優れた記憶力を持つことがあります。
LD(学習障害)
全般的な知的発達には問題がないものの、読む、書く、計算するなど特定の学習領域に困難がある障害です。職場では、文書作成や数値処理に課題があることもありますが、得意分野では高いパフォーマンスを示すことができます。
これらの特性は、適切な環境と理解があれば、職場での強みとして活かすことが可能です。
ADHD傾向のある人にあてはまりやすい例
ADHD傾向のある方は注意の向け方や集中の仕方に特徴があります。以下の3つの事例で、その特性と職場での活かし方を見ていきましょう。
事例1:好きな業務は誰にも負けないがそれ以外は苦手
Aさんの例(マーケティング会社勤務・28歳)
Aさんは新商品のアイデア出しやクリエイティブな企画立案では社内で一目置かれる存在です。アイデア会議では次々と斬新な発想を提案しチームを牽引します。しかし、日常的な事務処理や定型業務には集中が続かず、ミスが多発してしまいます。
・職場での工夫と成果
・得意な企画業務に特化した役割分担
・事務作業はチームメンバーと分担し、Aさんは創造的業務に集中
・短時間集中で成果を出すタイムマネジメントを導入
・結果としてAさんの企画から生まれた商品が複数ヒットし、会社の売上向上に大きく貢献
この事例ではADHDの特性である「過集中」を活かし、興味関心の高い分野で力を発揮できる環境を整えることで本人の能力を最大限に引き出すことができました。
事例2:発想力はあるがケアレスミスや抜け漏れがある
Bさんの例(IT企業・システムエンジニア・25歳)
Bさんはシステム設計で独創的なアイデアを提案し、技術的な課題解決に優れた能力を発揮します。しかし、詳細な仕様書作成や進捗管理ではケアレスミスや記載漏れが頻発し、プロジェクトに影響を与えることがありました。
・職場での工夫と成果
・ペアプログラミングの導入によりミスチェック体制を強化
・作業の可視化ツール(カンバンボード)を活用し進捗管理を明確化
・定期的な短時間レビュー会議を設け早期発見・修正を可能に
・Bさんのアイデアを活かしつつ品質管理は組織的にサポート
この取り組みによりBさんの優れた発想力を活かしながら組織全体でミスを防ぐ仕組みが構築され、プロジェクトの成功率が大幅に向上しました。
事例3:即断即決は得意
Cさんの例(営業職・32歳)
Cさんは顧客との商談で瞬時に状況を判断し、適切な提案を行う能力に長けています。競合他社との価格交渉や急な仕様変更にも素早く対応し、多くの成約を獲得しています。しかしじっくりと検討が必要な長期プロジェクトの計画立案は苦手です。
・職場での工夫と成果
・新規開拓営業や緊急案件対応を主な担当業務に設定
・長期計画が必要な案件は企画部門との連携体制を構築
・即断即決の良さを活かせるよう権限委譲を拡大
・結果として前年比150%の売上達成に貢献
Cさんの持つ「衝動性」を「迅速な判断力」として活かし、適切な役割分担により組織全体の営業力向上を実現した事例です。
ASDの方に当てはまりやすい例
ASD(自閉スペクトラム症)の方は規則性や一貫性を好み、特定の分野で高い集中力を発揮する特性があります。以下の4つの事例でその特性を職場でどう活かしているかを見ていきましょう
事例4:マルチタスクは難しいが1つの作業への集中力が高い
Dさんの例(品質管理部門・29歳)
Dさんは製品の品質チェックにおいて、細部まで見落とすことなく正確な検査を行う能力があります。一つの作業に集中している時の精度は非常に高く、不良品の発見率は部門内でトップクラスです。しかし、検査をしながら別の業務指示を受けると混乱してしまうことがあります。
・職場での工夫と成果
・作業時間中は集中できる環境を確保し割り込み作業を最小限に
・業務指示は作業開始前にまとめて伝える仕組みに変更
・休憩時間を活用した次の作業についての事前説明を実施
・結果として不良品流出を前年比80%削減し、顧客クレーム大幅減少を達成
この事例ではASDの特性である「シングルタスクでの高い集中力」を最大限に活用し、品質向上に大きく貢献しました。
事例5:ルール通り作業することが得意だが柔軟さがない
Eさんの例(経理部門・26歳)
Eさんは定められた経理処理手順を正確に実行し、ミスのない帳簿作成を行います。法令遵守意識も高く、監査対応では完璧な書類準備を行います。しかし、急な方針変更や例外的な処理が発生すると対応に時間がかかってしまいます。
・職場での工夫と成果
・標準業務はEさんが担当し、イレギュラー対応は上司や同僚がサポート
・新しい処理方法については事前に詳細なマニュアルを作成
・変更が予想される場合は早めの情報共有と準備期間を設定
・月次決算処理の正確性向上により監査法人からの信頼度が大幅向上
ルールに従った正確な作業というASDの強みを活かし、組織全体の信頼性向上に貢献した事例です。
事例6:読み書きの力があるが、堅苦しくなりがち
Fさんの例(法務部門・31歳)
Fさんは契約書の作成や法的文書の校正において正確で詳細な文章作成能力を持っています。法令の解釈や条文の理解も深く、社内の法的リスク管理に重要な役割を果たしています。しかし、顧客向けの説明資料では専門用語が多くわかりにくいとの指摘を受けることがあります。
・職場での工夫と成果
・社内向けの正式文書作成を主な担当業務に設定
・顧客向け資料は営業部門と協力して「翻訳」作業を実施
・Fさんの正確な法的知識を基にわかりやすい説明資料を共同作成
・結果として契約トラブルの発生率が前年比50%減少
専門性の高い文書作成能力を活かしつつ、組織的な連携により顧客対応力も向上させた事例です。
事例7:細かいことに気を付けることが得意だが大枠を見極めるのは苦手
Gさんの例(システム開発・テスター・27歳)
Gさんはソフトウェアのバグ発見において他の人が見落としがちな細かい不具合まで発見する能力があります。テスト仕様書通りの検証作業では100%の精度で実行し、品質向上に大きく貢献しています。しかし、プロジェクト全体の優先順位やどのバグを先に修正すべきかの判断は苦手です。
・職場での工夫と成果
・テスト実行に特化した役割を設定し、優先順位判断は別担当者が実施
・発見したバグの重要度分類はチームリーダーが担当
・Gさんの詳細な報告書を基に、効率的な修正計画を策定
・結果としてリリース後の重大バグ発生率がゼロを達成
細部への注意力という強みを最大限に活用し、全体最適は組織的にサポートすることで高品質なシステム開発を実現した事例です。
職場で配慮や環境調整を受けたほうがよいのか?
発達障害の特性を持つ方が職場で力を発揮するためには適切な配慮や環境調整が重要です。しかし、「配慮を求める=特別扱い」ではなく「能力を最大限に発揮できる環境作り」という視点で考えることが大切です。
配慮を受けるメリット
■本人のメリット
・自分の特性に合った働き方によりストレスが軽減される
・得意分野を活かすことでやりがいと達成感を得られる
・継続的に安定して働くことができる
・スキルアップや成長の機会が増える
■組織のメリット
・社員一人ひとりの能力を最大限に活用できる
・多様性のある職場環境によりイノベーションが生まれやすくなる
・離職率の低下により採用・教育コストが削減される
・インクルーシブな組織文化の構築により企業価値が向上する
具体的な配慮の例
■環境面での配慮
・集中できる静かな作業スペースの提供
・照明や音響の調整
・作業手順の可視化(チェックリストやフローチャート)
・ITツールの活用による業務効率化
■業務面での配慮
・得意分野を活かせる業務配分
・苦手な分野でのサポート体制構築
・柔軟な勤務時間制度の導入
・定期的な1on1ミーティングでのフォロー
■コミュニケーション面での配慮
・指示は具体的で明確に伝える
・締切や優先順位を明示する
・変更事項は早めに共有する
・フィードバックは建設的で具体的に行う
配慮を求める際の注意点
オープンなコミュニケーション 自分の特性や必要な配慮について、上司や人事担当者と率直に話し合うことが重要です。隠すのではなく建設的に解決策を見つける姿勢が大切です。段階的な実施 いきなり大きな変更を求めるのではなく、小さな調整から始めて効果を確認しながら徐々に最適化していくことが効果的です。相互理解の促進 配慮を一方的に求めるのではなく、組織の目標達成にどう貢献できるかを明確にしWIN-WINの関係を築くことが重要です。
発達障害の方が就職するときに注意したいポイント
発達障害のある方が就職活動を行う際、成功のために押さえておきたい重要なポイントがあります。
自己理解を深める
特性の把握
・自分の得意なことと苦手なことを明確にする
・どのような環境で力を発揮できるかを理解する
・ストレスを感じる状況や対処方法を知る
・必要な配慮や支援を具体的に整理する
専門的アセスメントの活用
心理検査や職業適性検査を受けることで客観的な自己理解を深めることができます。WAISやMSPAなどの検査結果は就職後の配慮依頼の際にも有効な資料となります。
企業研究と職種選択
企業文化の確認
・ダイバーシティ・インクルージョンへの取り組み状況
・障害者雇用の実績と体制
・働き方改革への姿勢
・社員の定着率や職場環境
職種適性の判断
・自分の特性を活かせる業務内容か
・苦手な分野をカバーできる環境があるか
・成長できる機会があるか
・長期的なキャリアパスが描けるか
就職活動の進め方
オープン就労 vs クローズ就労の選択
オープン就労のメリット
・必要な配慮を最初から受けられる
・理解のある環境で働ける
・専門機関のサポートを継続して受けられる
・ストレスが軽減される
クローズ就労のメリット
・一般的な選考プロセスで評価される
・幅広い企業・職種から選択できる
・昇進・昇格の機会が同等にある
・給与水準が高い場合が多い
どちらを選択するかは個人の特性や希望、企業の状況を総合的に判断することが重要です。
面接対策
自己PRのポイント
・特性を強みとして表現する
・具体的な成果事例を準備する
・困難な状況をどう乗り越えたかを説明できるようにする
・企業にどう貢献できるかを明確にする
質問への準備
よくある質問への回答を事前に準備し練習しておくことが大切です。特に、自分の特性に関する質問には正直かつポジティブに答えられるよう準備しましょう。
支援機関の活用
ハローワーク
障害者専門窓口では個別の相談支援や企業との橋渡しを行っています。
就労移行支援事業所
就職に向けた訓練や企業での実習機会を提供し、継続的なサポートを受けることができます。
障害者職業センター
職業評価や職場適応指導など、専門的なサービスを提供しています。
民間の人材紹介会社
発達障害に特化した人材紹介サービスを利用することで理解のある企業との出会いの機会が増えます。
入社後の定着に向けて
定期的な振り返り
入社後も定期的に自分の状況を振り返り、必要に応じて配慮の見直しを行うことが重要です。
継続的な自己啓発
自分の特性を活かしつつ、さらなるスキルアップを目指すことでより価値の高い人材として成長できます。
サポートネットワークの維持
職場の同僚や上司だけでなく外部の支援機関や同じ境遇の仲間とのつながりを大切にすることで、困った時に相談できる環境を維持しましょう。
発達障害は「治すべき障害」ではなく、「活かすべき特性」として捉えることが重要です。適切な理解と環境があれば発達障害の特性は大きな強みとなり、組織の成長にも貢献できます。自分らしく働ける職場を見つけるためにまずは自己理解を深め、積極的に情報収集と準備を行いましょう。
作業療法士 大石 純